合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!
このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.
リンクや広告について
当サイトには広告や別サイトへのリンクがありますので、ご確認ください。また、配信事業者はCookieを使用してウェブサイト閲覧履歴に基づく広告を配信しております。
貯蔵・取り扱いの基準
貯蔵技術基準(出題が多いです)
・許可、届出された数量、指定数量の倍数を超える
危険物、許可、届出された品名以外の危険物を
貯蔵・取り扱わない。
・みだりに火気を使用したり、係員以外の者を
出入りさせない。
・不要な物を置かない。
・貯留設備、油分離装置に溜まった危険物は、
随時くみ上げる。
・危険物の屑、カス等は1日に1回以上、安全な
場所で適切に処理する。
・危険物の性質に応じた、遮光、換気をする。
・危険物が残存している設備、機械器具、容器等を
修理する際は、安全な場所に置いて危険物を
完全排除した後に行う。
・保護液に保存している危険物は、保護液から露出
しない様にする。
貯蔵の基準
危険物と危険物以外の貯蔵
危険物と危険物以外の物品は原則として同時貯蔵は出来ない(危険物を保管している部屋で、関係のない物品は置いておけないと言うことです)
例外
屋内貯蔵所、屋外貯蔵所
危険物と危険物以外相互に1m以上の間隔を置く。
※試験に出題されないため詳細を省く。
屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所
※試験に出題されないため詳細を省く。
異なる類の危険物同士の貯蔵
類を異にする危険物は、原則として同時貯蔵は出来ない。
例外
屋内貯蔵所、屋外貯蔵所
定められた類、及び物品を類別毎にそれぞれまとめて貯蔵し、相互に1m以上の間隔を置く。
その他
・屋内外貯蔵所及び屋外貯蔵所において、
容器の積み重ねの高さは3m以下とする。
(第3・第4石油類及び動植物油類のみであれば4m
以下、機械により荷役する構造を有する容器のみ
であれば6m以下)
・屋外貯蔵所において、容器を架台で貯蔵する
場合の高さは6m以下。
・屋内貯蔵所において、危険物の温度が55℃を
超えない様に必要な処置をする。
・計量口は、計量するとき以外は閉じておく。
・元弁、注入口の弁、蓋は危険物の注入・排出以外
では閉じておく。
・屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の水抜き
口は、通常時閉鎖しておく。滞油、滞水した際には
速やかに排出する。
・被牽引自動車に固定された移動貯蔵タンクは、
牽引自動車に結合しておく。
移動タンク貯蔵所に必要な書類
・完成検査済証
・定期点検記録
・譲渡・引渡の届出書
・品名、数量または指定数量倍数の変更の
届出書
※上記の書類は備え付けのため、会社や事務所にあってはならない。
取扱技術基準
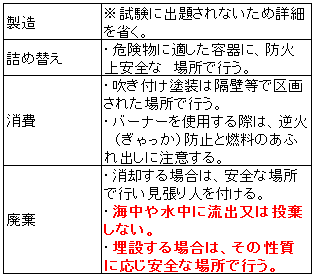
施設区分毎の取扱
給油取扱所
・直接給油する。
・自動車のエンジンを停止し、自動車は給油
空地からはみ出さない。
・空地には自動車の停止、駐車、物件の置物を
しない。
・物品販売等は、原則建築物の1階でのみ。
・自動車等の洗浄に、引火点を有する洗剤を
使用しない。
販売取扱所
・容器入りのままで販売する。
(オイル交換などは作業場で行うためOK)
・危険物の配合は配合室以外で行わない。
移動タンク貯蔵所
・貯蔵、取扱タンクに注入する際は、注入ホースを
注入口に緊結する。
・移動タンクから液体の危険物を容器に詰め
替えない。
(定められた容器に引火点40℃以上の第4類
危険物を詰め替える場合を除く(灯油など))
・注入ホースの先端部に手動開閉装置付きの
ノズルで行わなければならない。
・静電気防止のため、安全な注油速度で行う。
(流速を早くすることはNG。遅いなら遅いほど良い)
・静電気防止のため、危険物を移動貯蔵タンク
に注入する際には、注入間の先端を底部に
付けると共に、接地(アース)を行う。
・引火点40℃未満の危険物を注入する場合は、
移動タンク貯蔵所のエンジンを停止して行う。



